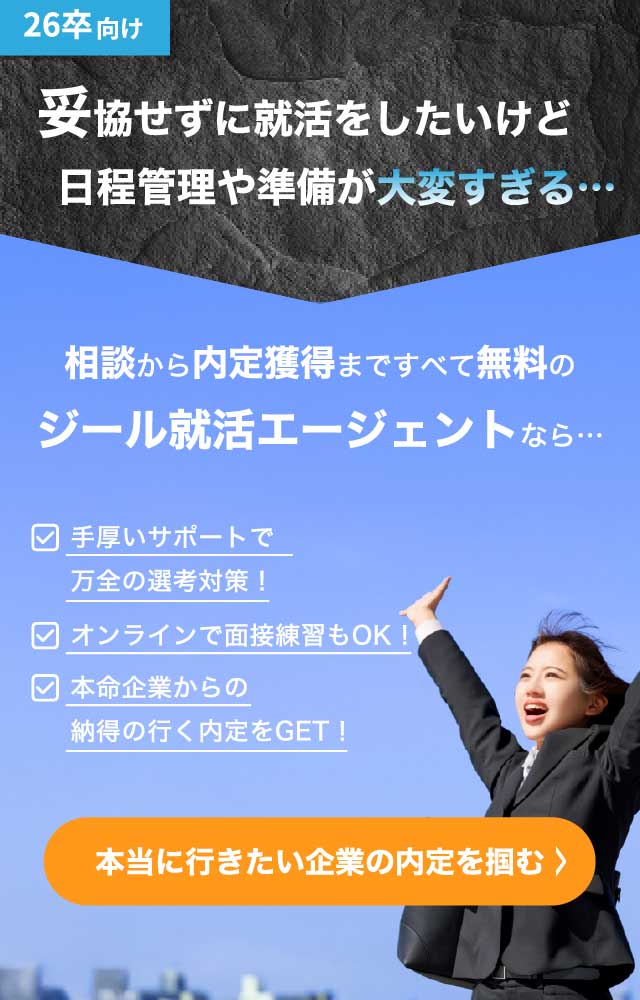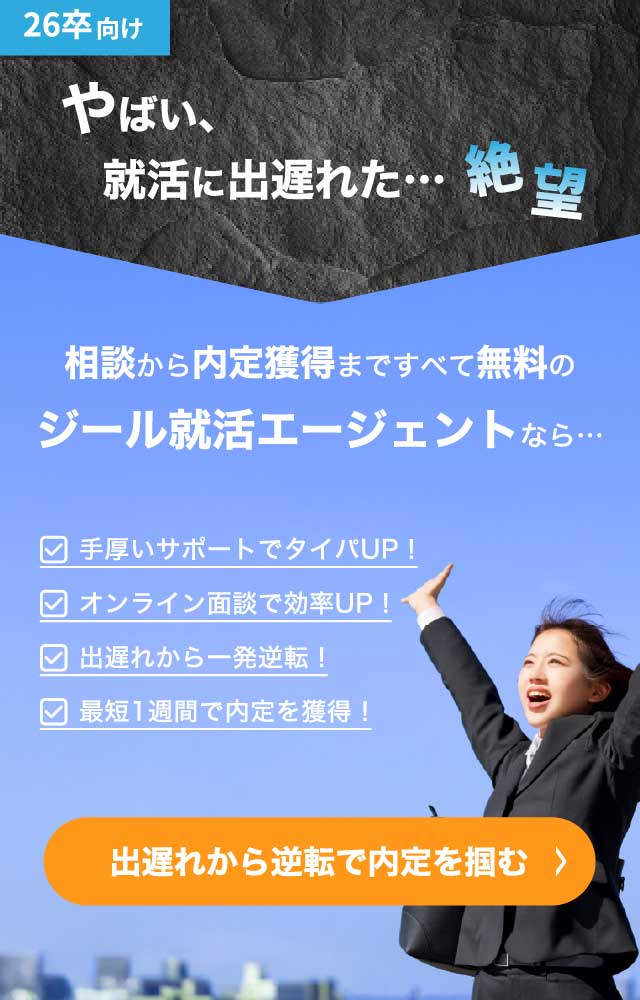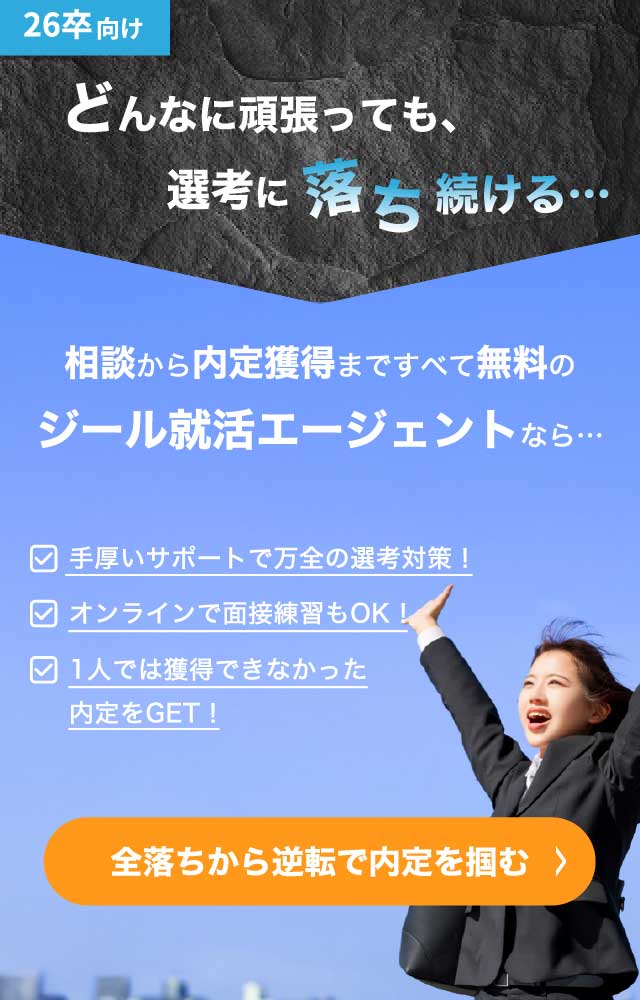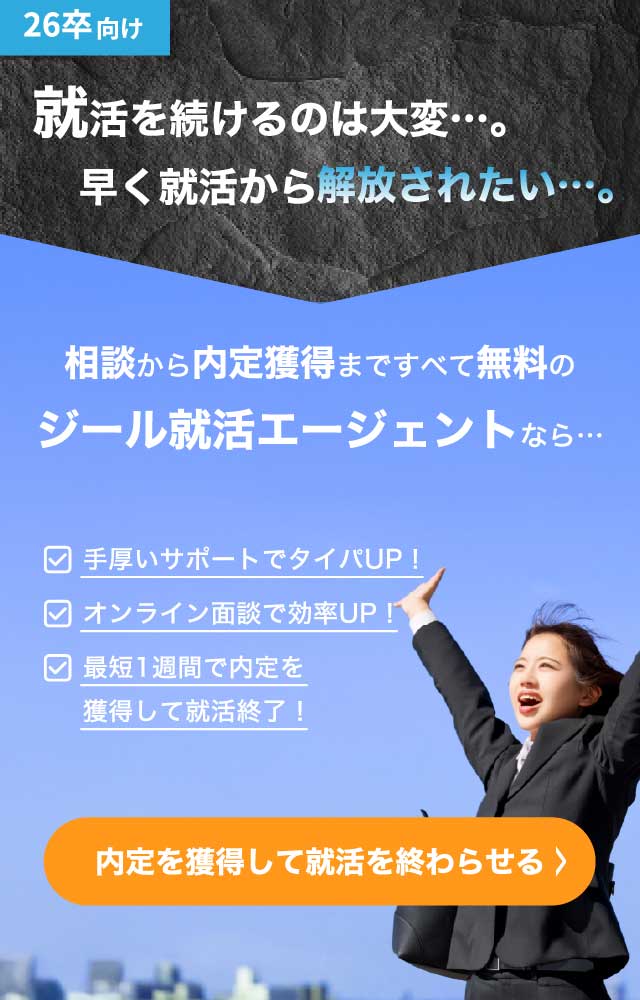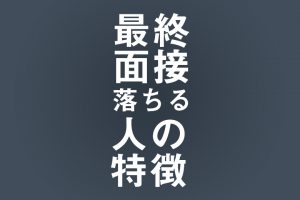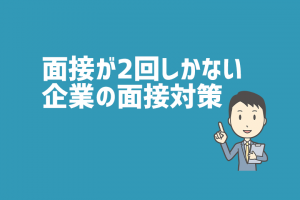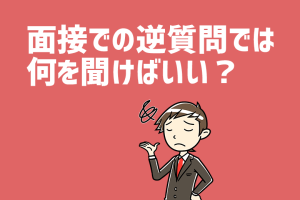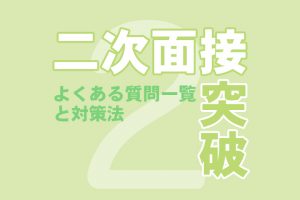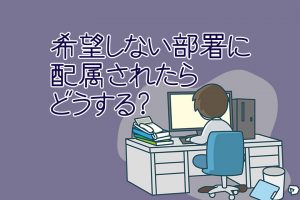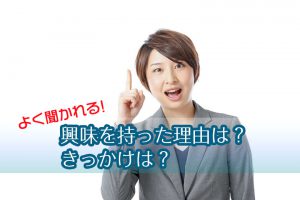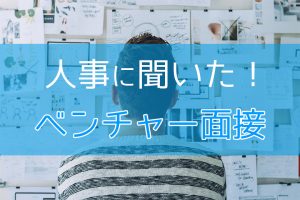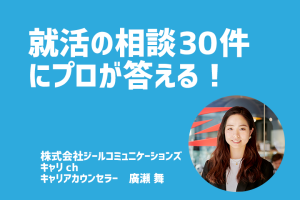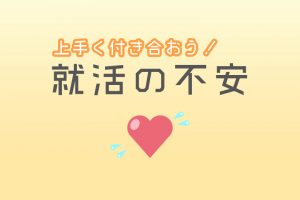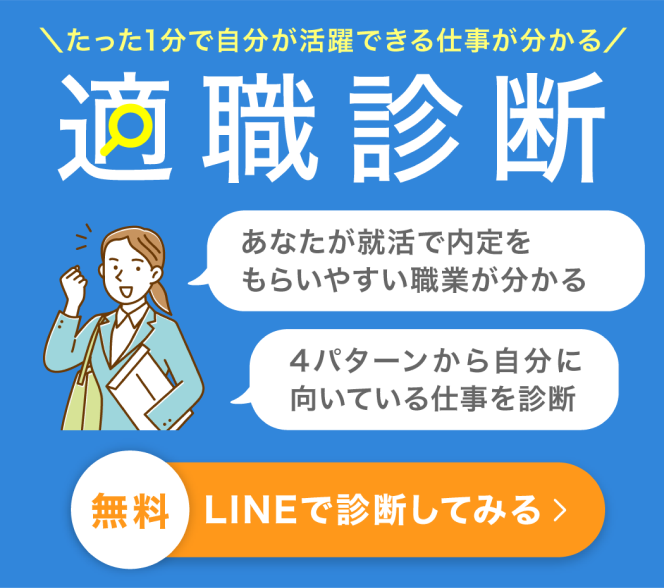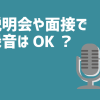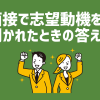最終面接の合格率はコレだ!合格率を上げる方法と「合格サイン」を共に解説
2022年11月2日
やっとの思いでこぎ着けた最終面接。内定に最も近い場ということもあり、気合が入っている人も多いのではないでしょうか。
就活は書類選考に始まり、一次面接、二次面接など、いくつかの面接を行う事でやっと最終面接へとたどり着くことができます。
そんな就活における選考にはそれぞれに「通過率」がある程度定められています。もちろん企業によってパーセンテージは異なってきますが、目安として参考になります。
では、最終面接の合格率はどれぐらいなのでしょう。
「最終面接で落とされることはあまりない」「入社への意思確認だから落ちる心配はない」なんて噂なども飛び交っていることから、最終面接の合格率は高いと思っている人も多いのではないでしょうか。
そんな最終面接の合格率ですが、約50%とされています。このパーセンテージはこれまでの選考の中でも最も高い数値とされているため、確かに数値だけを見れば受かりやすいと感じるでしょう。
しかし、100%ではない以上、最終面接に行けても内定をもらえないことはあるというのが事実ですし、最終面接は選りすぐりの優秀な人材が集まる場ですので、個人的な戦いとしては厳しいものとなります。
それに最終面接はれっきとした“選考の場”です。入社への意思確認をする場ではありません。そのため、最終面接に臨む以上、内定を勝ち取るための対策をしっかりと行わなくてはなりません。
努力から勝ち取った最終面接への切符。無駄にしないためにもこのコラムを読んで、合格率の仕組みから合格するための対策を確認していきましょう。
最終面接の合格率と仕組み

書類選考や第一面接などで「合格率」は異なってきますが、最も内定に近く、重要ともいえる“最終面接”ではどれぐらいの合格率なのでしょうか。
ここでは、そんな最終面接の合格率と仕組みについてご説明いたします。
最終面接の合格率は約50%
最終面接の合格率は約50%と言われています。多くの企業は「一次面接」「二次面接」「最終面接」の3段階に分かれており、一次面接約20~40%、二次面接は約20~%、最終面接は約50%と、最終面接が最も高い通過率とされています。
- [一次面接]約20~40%
→1人に割ける時間に限度があるため、「印象」から学生を判断する。効率よく選考を行うことから、通過率が低い傾向あり。 - [二次面接]約20~50%
→「企業理解度」や「志望度」で学生を判断する。最終に進める学生を選抜する中間時点のため、通過率は大幅に変動する傾向あり。 - [最終面接]約50%
→最終的に企業とマッチするか、誰に内定を出すかなどを判断する場。人数も絞られているため、必然的に通過率は高くなる。
面接ごとに目的が異なるため、それぞれの通過率・合格率は異なります。のちほど「最終面接でチェックしていること」より詳しく解説しますが、最終面接では「人数がある程度絞られることから、必然的に通過率が高くなる」ことなどが、通過率が高くなる要因と一つとされています。
合格率は条件によって異なる
最終面接の合格は約50%とされていますが、この数値は企業や条件によって大きく異なってきます。具体的にどのような要因から合格率が変動するのか、下記からご覧ください。
しかし、これらはあくまで目安に過ぎないため、参考程度にご覧ください。
- 面接回数2回→30~50%
- 面接回数3回→50~70%
- 面接回数4回以上→70%以上
■面接回数
面接回数によって合格率は変動します。多くは「一次面接」「二次面接」「最終面接」の3回ですが、企業によって2回、5回以上としている場合もあります。
面接回数が多ければ多いほど、合格率が高くなる仕組みです。面接回数が多いということは、最終面接までにいくつかの条件をクリアし、ある程度人材を絞っていることになるため、人数も少なくなりますし、選りすぐりの人材が残っていることから合格率が高まります。
反対に回数が少ないと「選考」を重視しているため、見極めるという目的から一次面接、二次面接と合格率にあまり差が開かなくなります。
- 大手規模×採用予定人数10~100人=20~40%
→大手規模の企業(大手企業・有名企業)は人気があるため、採用予定人数が多くても少なくても合格率が低い傾向があります。また、大手企業のように人気のある企業では“内定辞退者が出ないことを想定”して、決められた人数のみを確保する傾向があり、これらも内定率が低くなる要因とされています。 - 中小規模×採用予定人数100人=50~80%
- 中小規模×採用予定人数20人=50~80%
→中小規模の企業(中小企業・ベンチャーなど)は、採用予定人数が多くてもその分応募者数も少ないため、合格率が高い傾向があります。
■採用予定人数
採用予定人数だけで変動するのではなく、会社規模(会社の人気度)によってパーセンテージは変わってくる。
[例]
また、人数が少ない場合でも、中小企業やベンチャー企業などでは、“辞退者が出ることを想定して学生を確保”している場合が多いため、合格率も高くなります。人が集まらなければその分、合格率も上がります。
- 第一回目(6月頃)→50%
- 中盤(6~10月頃)→30%
- 最終(追加募集)→10%
■時期
最終面接は、内々定を提示する6月頃に第一回目が行われ、、内定式前までに第二回、さらに内定辞退者が出た後に行われる「追加募集」として第三回目が行われることがほとんどです。そして、これらの時期によっても合格率は異なってきます。
第一回目に行われる最終面接が最も合格率が高く、時期が遅くなっていくにつれ、合格率は下がっていく仕組みです。第一回目では辞退者が多く出ることを予想し、多めに内定を提示していましたが、中盤時期ではある程度内定者を確保したうえでの最終面接となるため、空いた席が少なく、合格率も下がります。
そして、最終時期では追加募集がほとんどのため、採用枠が1~2人程度と少なく、必然的に合格率が下がる仕組みです。さらに、最終時期ということもあり、当初よりも優秀な学生が減ったことで、「無理やり合格者を出さない」としている場合もあり、合格率が下がる要因の一つとなっています。
- 大手企業→30%
- 中小企業→30~50%
- ベンチャー企業→30~50%
■会社規模
大手企業、中小企業、ベンチャー企業それぞれの会社規模によって合格率が変動します。
大手企業は人気がありますし、応募者も多く、辞退者が出ないことを見込んでの採用となるため、合格率が低くなる傾向があります。さらに大手企業はライバルの質も高いため、そもそもの選考突破が難しいとされています。
中小企業やベンチャー企業は辞退者が出ることを想定し、あらかじめ多めに内定を提示する傾向があるため、大手企業よりも合格率が高くなりますが、採用予定人数などにもよるため、合格率は30~50%と差が開く形です。
■職種
職種によって合格率が多少異なる場合があります。専門的な技術を持っている技術職では合格率が高くなりますが、ライバルの多い営業職や、そもそも募集されていることが少ない事務職などでは人が集まりやすいため、競争率が上がり、合格率も下がる仕組みです。
■推薦
「学校推薦=落ちない」というイメージがあると思いますが、残念ながらそうとは限りません。つまり、合格率は100%ではないということです。
推薦は企業が大学にお願いしている人数に学生がどれぐらい応募するかによって合格率は変わってくるため、具体的な数字を出すことはできませんが、推薦だから必ずしも受かるとは限らない(合格率は100%ではない)ということを覚えておきましょう。
面接回数や時期などによって最終面接は変動するため、必ずしも最終面接が通過しやすいというわけではありません。それに最終面接は「意思確認の場」ではなく、「選考の場」ですので、最終面接に臨む以上、しっかりと対策をする必要があります。
もし、面接の対策をしたい場合は、キャリアプランナーに頼ることをオススメします。キャリchでも専属のカウンセラーがマンツーマンで対応いたしますので、「面接サポート」からご予約ください。
最終面接でチェックしていること

様々な条件によって最終面接での合格率は異なってきますが、最終面接でチェックしていることは企業も共通です。
先ほど、「人数がある程度絞られることから、必然的に通過率が高くなる」と述べましたが、人数だけに限らず、これらのチェックポイントから合否を判断しているため、「最終面接だから受かる」と浮かれず、どのようなことをチェックされているのかを確認しておきましょう。
志望度の高さの再確認
最終面接では「志望度の高さ」を再確認しています。企業側はこれまでの面接を通して学生の「志望度の高さ」をチェックし、志望度が高いと判断された学生のみを最終面接へと招待しました。
なぜここまでして「志望度の高さ」をチェックしているのか、その理由は、志望度の高さから「入社後に活躍が見込めるか」どうかを判断しているからです。
企業は採用活動に膨大なお金と時間をかけているため、「ここまでのかけたのだから企業のためになる人が欲しい」と思っています。そしてそれらを評価する具体的な指標こそが、この“志望度の高さ”なのです。
志望度が高ければ企業への理解も深いですし、企業への愛も感じます。そして企業への愛情が深い人は「企業のため」に働いてくれるため、入社後も活躍が見込めるのです。
最終面接では役員や社長など、会社の経営に大きく関わる人物が面接官を務める場合が多いので、とくに入社後の活躍について厳しくチェックしています。ですから、一次面接から重要視されている「志望度の高さ」を、最終面接でも再度確認しているというわけです。
企業が目指す方向を理解しているかの確認
最終面接では志望度の他に、「企業が目指す方向を理解しているか」の確認をしています。志望度の高さから学生の熱意や、仕事への期待を見込めたとしても、企業が目指す方向を理解していないと思うような成果を残すことはできません。
今までの面接では、学生の人柄や能力(スキル)などをチェックし、企業が求める条件に当てはまると判断された人たちが最終面接へと進むことができました。つまり、今までの面接であなたは「一個人としては優秀」だと判断されたということです。
しかし会社というものは一つの大きな組織です。いくら一個人が優秀だとしても、組織として働いて行くことができなければ、その能力はつぶれてしまうのです。
つまり、会社で働くという以上、一個人だけの能力だけではなく、組織として働いていけるかどうかも重要だということです。そんな「組織」として働いていけるかどうかの判断こそが、“企業が目指す方向を理解しているかどうか”なのです。
簡単にいえば、いくら優秀でも会社の方針に背く人は活躍が見込めないし、内定ももらえない、ということです。
一緒に働きたいと思えるかの確認
最終面接では、これから仲間になるかもしれない今のこの場にいる学生と“一緒に働いたい”と思うかどうかを確認しています。
内定を出すかどうかを判断するために仕事への貢献や組織への対応力、学生自身の能力などは確かに大切です。
しかし、最終的に内定を出すかどうかを判断するのは「企業側の気持ち」です。つまり、いくらすごい能力を兼ね備えていても、いくら企業への理解を深めていても、“一緒に働きたい”と企業側が思わなければ最終的に「内定」を出すことはないのです。
最終面接は「内定」を出すかどうかを判断する場ですので、常に「入社後」を見越して学生を見極めています。会社に受け入れる以上、仕事への貢献度はもちろんですが、一緒に働きたいと思われることも重要だということです。
もし、最終面接の練習をしたい場合は、キャリchの「模擬面接」を利用してみてください。就活のプロであるキャリアカウンセラーが丁寧に対応いたします!
最終面接での合格率を上げるための方法

最終面接では「内定」を出すかどうかを判断する場のため、常に「入社後」を見越して学生を見極めています。つまり、最終的に選ばれる学生になるためにはしっかりとした対策が必要だということです。
一次面接や二次面接に比べたら確かに合格率は上がりますが、その分ライバルの質も高いということですので、負けないようにしっかりと対策をしていきましょう。
企業研究の再確認
最終面接に挑む前に企業研究の再確認を行いましょう。先ほども述べたように、最終面接では志望度の高さをチェックされているため、志望度の高さを示すためにも企業理解を深めていることをアピールしていかなくてはいけません。
それに、企業が目指す方向を理解しているかどうかもチェックポイントとなりますので再度、企業について理解を深めていくことは大切です。
また、最終面接は「内定」が出るかどうかが決まる場ですので、新たな気持ちで企業に対して熱意を伝えるためにも、なぜこの企業を志望したのか、企業の魅力は何かなどといったことを再確認することがとても大切です。
最終面接に進めたということで、求めている人材だと評価されていることは確かですから、後は企業理解からしっかりと自分の思いを伝えていけるようにしましょう。
最終面接ならではの質問を対策する
最終面接では、“最終面接ならではの質問”がいくつかあります。どの企業でも聞かれることの多い質問ですので、下記から質問例と回答のポイントをチェックしていきましょう。
■「改めて志望動機を教えてください」
一次面接などで述べていた志望動機を使い回すのではなく、今までの選考を通して感じたことなどを述べ、志望動機に深みを出しましょう。
■「弊社は第一志望ですか?」
“即答”で第一志望と答えます。即答できなかったり、第一志望群などといった答え方ではマイナス印象になりますし、入社意欲を疑われてしまうため、即答できるようにしておきましょう
■「会社ではどのような役割を担いたいですか?」
具体的にこの会社で実現したいことを述べる。業務内容や企業方針などを理解したうえで発言すると好印象です。
■「〇年後、あなたはどのようになっていたいですか?」
役職などの名前を出すなど、具体的にどうなっていたいかを答えられるようにする。将来のビジョンは“この会社”でのものになるため、「結婚してマイホームを購入する」などといったプライベートな回答をしないようにしてください。
学生の入社意欲や志望度の高さ、企業とのマッチを図るような質問をされるという特徴があります。それぞれ企業への理解が深くないと答えられない質問ですので、しっかりと再度企業研究を行いましょう。
逆質問で再アピール
最終面接突破の最大のカギは「逆質問」です。逆質問は自分をアピールできる最後のチャンスですので、「最後に何か質問はありますか?」と聞かれたらしっかりと質問をしていきましょう。
ここではいくつかオススメな逆質問についてご紹介していきます。
■業務内容や入社を前提とした質問
「業務内容」を聞く質問では、仕事に取り組む姿勢をアピールできますし、企業と学生との間で業務内容のイメージを共有できるため、企業にとって好印象な質問内容です。しかし、HPを見ればわかるようなことを質問してしまうのはかえって悪印象なので注意してください。
「入社を前提」とした質問では、仕事に対するやる気をアピールできますし、企業側もその学生の将来像がイメージしやすく、そして判断もしやすくなるので、オススメです。しかし「採用される前提」と混合しないように注意しましょう。
■長所・強みをアピールする
逆質問を通して自分の長所や強みなどをアピールするのも良いでしょう。もしかしたら逆質問の前に「長所は何ですか?」と聞かれているかもしれませんが、長所や強みはたくさんアピールするに越したことがないので、積極的にアピールしていきましょう。
しかし全く同じ長所を繰り返し言ってもあれですので、言い方を変えて伝えましょう。たとえば、「コミュニケーション能力がある」という長所なら、「聞き上手」「場を盛り上げることが得意」などと言い換えることができるため、言い方を変えてたくさん自分をアピールしていきましょう。
逆質問は5つ程度用意しておくと良いでしょう。逆質問として聞こうとしていたものも面接官から質問される場合もありますし、1,2個しか用意せず、時間が余ってしまうと熱意がないと捉えられてしまう可能性もあるので、5つ程度は必ず用意しておきましょう。
最終面接の練習や逆質問の対策をしたい場合は、ぜひキャリchの「模擬面接」を利用してみてください。プロのキャリアカウンセラーがマンツーマンで対応します!
お礼メール・お礼状を送る
最終面接終了後には「お礼メール」「お礼状」を送りましょう。お礼メールやお礼状を送ることで良い印象を残せますし、ここまで選考をしてくれた人に対して感謝の気持ちを述べるのはとても良いことです。
基本的にメール、手紙どちらでもOKですが、どちらにせよ面接が終わったらすぐに送るようにしてください。メールの場合、夜中にメールを送るのは迷惑となりますので、営業時間内(お昼休憩の12:00~13:00と就業終業の1時間を除いた10:00~17:00の間)に送ります。
お礼メールには、面接をしてくれたお礼や、面接を通して感じたこと、入社への意気込みなどを書きます。
お礼メールやお礼状を送ることで直接合否へと影響するとは断言できませんが、あるとないとではある方がよい印象を残せることは間違いないので、必ず送りましょう。
面接官の行動から「合格サイン」は読み取れる?

最終面接は「内定」に最も近い場となるため、常に内定や合格などといったことを意識してしまうものです。手ごたえのある面接にしたいと思うでしょうし、できることなら早い段階で「内定」かどうかを知りたいと思うでしょう。
今回キャリchではそんな人たちのために、最終面接において、面接官の行動から「合格」を読み取ることができるのかについて解説します。
読み取れる場合もある!
最終面接では「内定は決まっており、社長などが最終確認をする場」としている企業や、「早い段階で合否を決めている」企業などがあることから、面接官の行動である程度「合格サイン」を見抜ける場合があります。
しかし、このような行動を示さない場合もありますし、「選考」を目的に最終面接が行われることがほとんどですので、あくまで参考にしかすぎません。ですので、「これをされたらから合格だ」と舞い上がらないようにしましょう。
- 面接時間が長い
→学生に興味を持つことで、自然と質問数や会話が増えることで時間が長引く。 - 他社の選考状況を聞かれる
→「他に取られたくない」という思いから聞く場合がある。他社の面接前に内定を提示することも。 - 最後まで熱心に話を聞いてくれる
→興味を持っており、深く学生を見極めていくために話を熱心に聞いている。 - 面接後に配属先の上司などに会わされる
→すでに入社後を見越しての行動のため、企業側からの行動であれば合格の可能性は高まる。 - 「ぜひ働いて欲しい」などと言われる
→企業側からのストレートなアプローチ。しかしこの言葉で内定が確定したわけではないので注意。 - 最後に握手をされる
→友好的な証とされる握手。最終面接でされるということで「入社後もよろしく」「内定承諾してね」などといった意味が込められている可能性が高い。
どの行動も、学生に興味を示している行動だということがわかると思います。学生自身もこのような行動をされれば「まさか?」と気づけるような行動こそが、合格サインである場合があるので、覚えておくと良いでしょう。
反対に、「不合格サイン」としてあげられるものもいくつかあるので、ご紹介します。
- 面接時間が短い
- 笑顔がない
- 回答がそっけない
- 掘り下げた質問をされない
- 明らかにそっけない
このような行動では「不合格」である場合がありますが、“あえて”このような行動をする面接官もいるそうです。そのため「これをされたから不合格だ…。」と落ち込むのではなく自分の実力を信じましょう。
しかし参考程度にしかならない
繰り返しになりますが、これらの合格サイン、不合格サインはあくまで参考に過ぎません。これらの行動をしても不合格になることはありますし、今までと特に変わりない態度から合格となる場合もあります。
また、「ぜひ入社してほしい」などと決定的なことを言われても、あなたの後に面接を行った人の方を高く評価してしまえば、この言葉は意味のないものとなります。
ですから、これらの行動に振り回されるのではなく、どんな結果になろうと悔いのない面接にするためにもしっかりと対策をしましょう。自分の実力のみを信じるのです。
おわりに
最終面接の合格率は今までの選考に比べて高い傾向がありますが、条件によって異なってくることを覚えておきましょう。
「最終面接は意思確認」というイメージも横行していますし、対策をおろそかにしている人が多くいますが、最終面接もれっきとした「選考」ですので、いくら合格率が高いからといって対策をおろそかにしてはいけません。
最終面接前には再度企業研究をし、最終面接ならではの質問などに備えましょう。もし、対策に自信がなかったり、最終面接が怖いという人はぜひキャリchを頼って下さい。
キャリchが開催するイベント「再就活サポート」では、最終面接に特化した対策からサポートを行い、納得のいく企業からの内定獲得をお約束しています。あなたが一番輝けるかたちで最終面接へと見送ります。ぜひ参加してみてください。
再就活サポートに参加しよう!
この記事の監修者

平崎 泰典
株式会社ジールコミュニケーションズ
HR事業部マネージャー
2016年に入社後、企業向けの採用コンサルティング業務を経て、就職・転職希望者に対する個別就職支援を担当。「キャリチャン」「合説どっとこむ」において年間100回以上の就職・転職セミナーの講師も務める。
主な担当講座に「営業職や種類が適性がよくわかる解説講座」「手に職をつけられる仕事解説講座」などがあり、これまで3,000名以上に対して講座を実施。
就職支援では「自己分析」と「業界研究」を得意として、就活初期の学生や求職者を相手に基礎からサポートを行う。年間1,000名以上の内定獲得を支援。